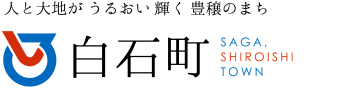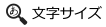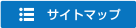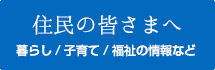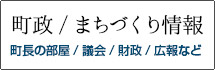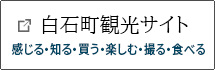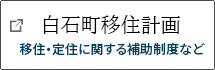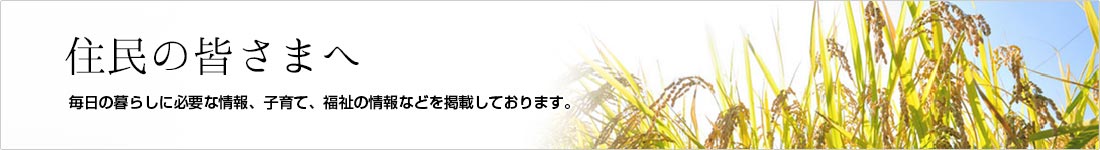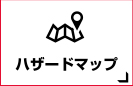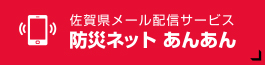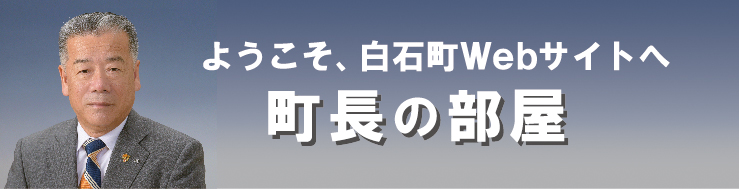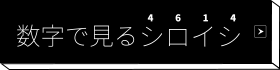あるある文化財VOL.176 英彦山信仰
英彦山(ひこさん)は福岡県と大分県の境にそびえる標高約1,200mの山であり、古来より修験道(しゅげんどう)(日本古来の山岳信仰(しんこう))の聖地として信仰されてきました。現在は、英彦山神宮が立地しています。御祭神は、天照大御神(あまてらすおおみかみ)(日神)の御子の天忍穂耳命(あめのおしほみみのみこと)であり、鎮座するその山は「日の子の山」すなわち「日子山(ひこさん)」と呼ばれていました。弘仁(こうにん)10年(819)に嵯峨(さが)天皇の詔(みことのり)により「日子」を「彦」に改め、さらに享保(きょうほう)14年(1729)に霊元法皇(れいげんほうおう)の院宣(いんぜん)により「英」の一字が与えられ「英彦山」となりました。
英彦山は、豊前(ぶぜん)国(現:福岡県の一部)に属しますが、中央の朝廷、九州一円など広く信仰を集めました。江戸時代、特に信仰を寄せ手厚く支援した大名の一つが佐賀藩の大名であった鍋島家です。
佐賀藩初代藩主勝茂(かつしげ)は寛永(かんえい)14年(1637)に青銅製の鳥居である銅鳥居(かねのとりい)を寄進しており、国の重要文化財に指定されています。
英彦山の社殿は、幾度となく火災に遭い消失を繰り返していますが、その再建を鍋島家が支援しています。英彦山中岳山頂に建つ現在の御本社(上宮)は天保(てんぽう)13年(1842)~弘化(こうか)2年(1845)にかけて10代藩主斉正(なりまさ)(直正(なおまさ))によって再建されたものです。
藩主の信仰が篤かった佐賀藩では、英彦山信仰が領民にも広がり、英彦山詣でが人気を集めました。九州において特に肥前(現:佐賀県・長崎県)は信仰が盛んであり、長野覺氏による江戸時代の1~8の等級に分けられた信仰圏の中でも、白石地域は第1等級に分類されており特に信仰が盛んであったことが分かります。町内の横手上には、英彦山神社が建立されているのも信仰を示す一例でしょう。
江戸時代、須古を治めた須古鍋島家も英彦山を深く信仰しました。龍造寺隆信の甥にあたる2代須古影庵(えいあん)(信明(のぶあき))が病気平癒(へいゆ)を感謝して寛永15年(1638)に「仁王般若経(にんのうはんにゃきょう)(色紙経)」を英彦山へ奉納しています。仁王般若経は、法華経(ほけきょう)や金光明経(こんこうみょうきょう)ともに護国三部経の一つとして尊重されました。奉納された仁王般若経は、金銀箔・雲母(きら)を使用した平安時代の装飾経です。平安時代の装飾経の多くが法華経である中、現存する唯一の仁王般若経の色紙経として貴重であり、国の重要文化財に指定されています。江戸時代、英彦山では毎月28日に仁王般若経の教説に基づく月次仁王会(つきなみにんのうえ)が開かれていました。
※英彦山神宮、福岡県添田町役場まちづくり課より史料の提供等ご協力をいただきました。ありがとうございました。
※写真・資料等につきましては、著作権の観点から掲載しておりません。ご理解の程よろしくお願いします。
〈参考文献〉
九州歴史資料館『霊峰英彦山―神仏と人と自然と―』平成29年
重藤秀世『2019年版 山と高原地図 57福岡の山々・宝満山・英彦山』昭文社 令和元年
長野覺『英彦山修験道の歴史地理学的研究』名著出版 昭和62年
PDF形式のファイルをご覧いただくには、アドビ システムズ社から無償提供されているAdobe ReaderTM(別ウインドウが開きます)プラグインが必要です。
このページに関するお問い合わせ先 生涯学習課 生涯学習係 電話(直通):0952-84-7129