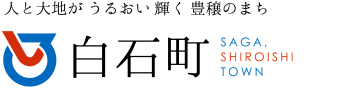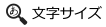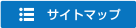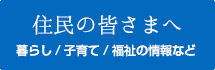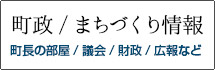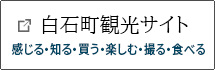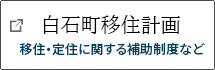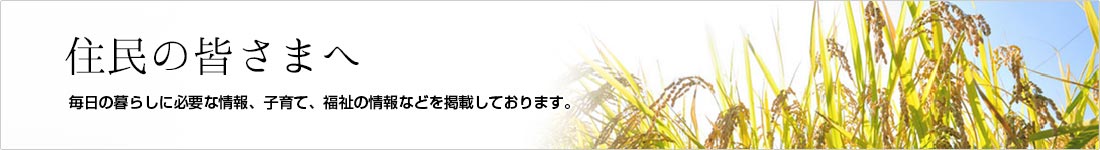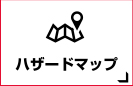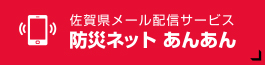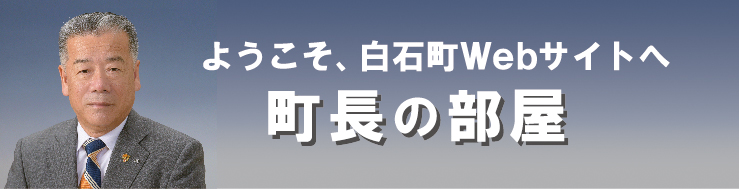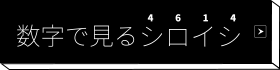あるある文化財VOL.183 電燈建設紀念碑
電燈建設紀念碑
百貫(ひゃっかん)・琴平海童(ことひらかいどう)神社の鳥居西側に「電燈建設紀念碑(でんとうけんせつきねんひ)」と刻まれた高さ125cmの石碑が建てられています。石碑右側面には、建設委員として9名の名前が、左側面には「大正十年八月 發起人漁業者中」と刻まれています。
日本において最初の電気照明は明治11年(1878)に中央電信局開局の祝宴(しゅくえん)で点灯されたアーク灯とされています。明治19年(1886)、現在の東京電力の前身である東京電燈によって電力供給事業が開始され、電灯(白熱電球)の本格的な普及が始まりました。
佐賀県内においては、明治39年(1906)に広滝水力電気株式会社が設立され、明治41年(1908)に広滝水力発電所が完成し、佐賀市および神崎方面への送電が開始されました。その後、広滝電気は明治43年(1910)に唐津電灯株式会社を買収し、同年設立された九州電気に合併されました。九州電気は明治45年(1912)に博多電灯鉄道株式会社と合併し、九州電灯鉄道となり、更に大正11年(1922)に九州電灯鉄道は関西電気株式会社と合併し東邦(とうほう)電力が発足します。
その後、東邦電力は昭和15年(1940)までに県内の電力供給事業会社を合併し、県内大部分の電力供給を行うようになります。東邦電力は昭和17年(1942)に解散され、戦後電力再編により中部電力・関西電力・四国電力・九州電力の4社に継承されることになります。
町内において電灯の導入された時期については、『須古村片影(すこそんへんえい)』において「大正7年(1918)1月25日、肥前(ひぜん)電鉄会社と契約、本村馬田(うまだ)より新町(しんまち)を経へ村役場に至り、電燈を架設したり。」とあります。『白石町史』において大正10年(1921)、「この頃白石地方に10燭(しょく)電灯がつき始まる」、『福富町誌 続編』において大正7年(1918)、「電灯ともる(上、中、下)」(注:上区、中区、下区)、『有明町史』において「大正10年(1921)~大正12年(1923)の間である。」とあり、大正期に、電線の敷設及び電灯の普及が始まったと思われます。
白石地方一帯に当初電力を供給したのが、嬉野(うれしの)に拠点を置いた肥前電気鉄道株式会社でした。鉄道事業廃止に伴い昭和7年(1932)に肥前電気と改称し、昭和12年(1937)に前述の東邦電力に合併されました。
近代化の象徴ともいえる電気の灯りが夜を明るく照らしたことは、人々にとって大きな驚きと喜びであり、紀念碑はその当時の事の重大さを私たちに教えてくれます。
〈参考文献〉
有明町教育委員会『有明町史』昭和44年
石﨑有義「白熱電球の技術の系統化調査」『技術の系統化調査報告共同研究編』第4集 国立科学博物館 平成23年
加島 篤「日本における定額電灯制と電球貸付の変遷」『北九州工業高等専門学校研究報告』第46号 平成25年
佐賀県教育委員会編『佐賀県の近代化遺産-佐賀県近代化遺産(建造物等)総合調査報告書-』平成14年
白石町史編纂委員会『白石町史』昭和49年
福富町誌編さん委員会『福富町誌 続編』平成4年
吉岡達太郎『須古村片影 活字本』平成12年
PDF形式のファイルをご覧いただくには、アドビ システムズ社から無償提供されているAdobe ReaderTM(別ウインドウが開きます)プラグインが必要です。
このページに関するお問い合わせ先 生涯学習課 生涯学習係 電話(直通):0952-84-7129