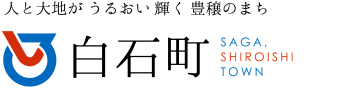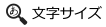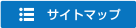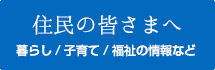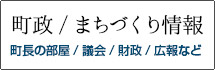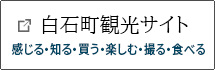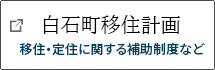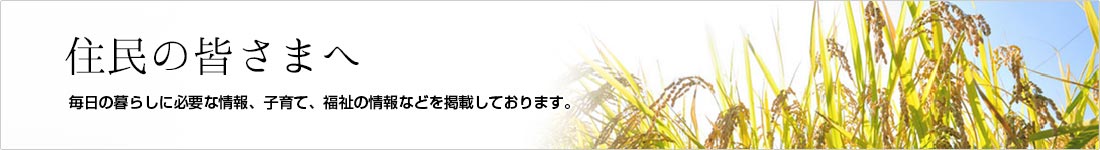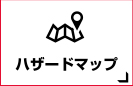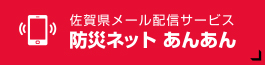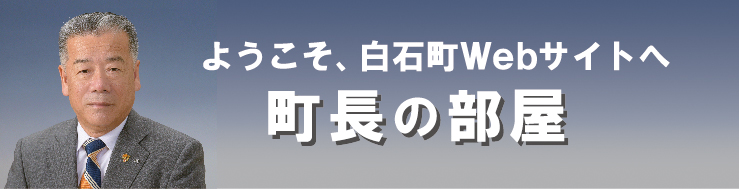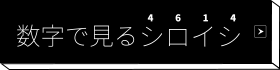あるある文化財VOL.200 煮じゃあ(煮菜)

煮じゃあ
白石中学校所属川田孝子栄養教諭提供
令和3年12月4日、認定NPO法人21世紀構想研究会主催第16回全国学校給食甲子園において、白石町学校給食センターが準優勝(野口医学研究所賞)を受賞されました。その際のメニューの中に、郷土料理「煮じゃあ」が含まれていました。
「煮じゃあ」は、主に秋のお供日(くんち)(白石町では10月19日の妻山・六角(ろっかく)・福富・稲佐(いなさ)各神社の例祭日)に食べられる郷土料理です。『白石地方の方言』(平成3年)には、「里芋、ちくわ、小豆などをごった煮にした、佐賀地方の家庭料理。※主に供日料理としてつくられる。」ものが「にじゃあ」とあるように、旧白石町では「にじゃあ」と発音するのが一般的なようです。
『佐賀の方言』上巻(昭和45年)には、「煮ツケ。「煮コロガシ」ともいう。鹿島地区などで多く使われる。」ものが「ニジャー」とされ、『佐賀の郷土料理』(昭和59年)では、塩田町の「煮じゃー」が紹介され、『佐賀弁一万語』(平成7年)には、「(煮菜)煮つけ。煮ころがし(鹿島)。お供日のがめ煮に似たもので、竹輪、小豆、いりこ、などを加えたもの(江北)。」が「にじゃー」とされています。これらを見ると、鹿島市・塩田町・江北町では「にじゃー」と発音するのが一般的とすることができるでしょうか。ただ、『佐賀の郷土料理』では、江北町の代表的な郷土料理として「煮じゃあ」が紹介されています。
『佐賀県の民俗』下巻(昭和49年)には、旧白石町大字福吉での聞き取りで「特別の祝の時の献立」のなかに、「供日(氏神祭日)」の料理として「にじゃー(味噌汁に小豆・ごぼう・れんこん・いものこ・こんにゃく等を入れ、味付けの小魚や具を混ぜたもの)」が、同じく旧有明町大字深浦での聞き取りでは、「祝儀の時の食品」のなかに「煮じゃー」が挙げられています。「煮じゃー」の具体的な具材が分かりませんが、「煮じゃあ」と同じと考えてよいでしょう。
佐賀方言の特徴の一つとして、単語の長音化が指摘されています。例えば、「今日」を「きゅー」、「菜:おかず」を「しゃー」と発音するなどで、「今日のおかずは鯛と大根だよ」を「きゅーのしゃーは、ちゃーとじゃーこんよ」と発音します(『佐賀を「知る」、「発見する」、「好きになる」佐賀巡り』)。「煮じゃあ」は漢字で書くと「煮菜」で、文字通りおかず・副食物を煮込んだ食品のことです。「菜」は方言で「しゃあ」や「しゃー」と発音し、「煮菜」の発音が「にじゃあ」や「にじゃー」となります。どちらの発音になるかは、地域や世代の違いによるものでしょう。
ちなみに、広島県福山市には、畑から収穫した季節の食材を使った郷土料理「煮じゃあ」があります。「煮菜(にざい)を備後地方の方言で「煮じゃあ」と」呼ぶそうです(福山市ホームページ)。
さて、白石町の「煮じゃあ」の具材として赤貝、小豆などの豆類、れんこんが欠かせないものとされていますが、「小豆は必ず入れんば」とか、「赤貝の入っとらん煮じゃあは「煮じゃあ」じゃなか」とか言われます。「煮じゃあ」の具材も、上記のようにその発音の仕方と一緒で、作る世代、家庭や地域毎の違いがあるのでしょう。
冒頭に記したように、「煮じゃあ」は主にお供日という「ハレ(晴れ)」という特別の日に食べられる郷土料理ですが、何時から食べられるようになったのか、とよく聞かれます。これに関しては、現時点では明確な答えを出すことができません。政治的・軍事的な事件や災害の発生などは、公的・私的に記録されることが多く、後世において何時と確認することができますが、民俗的な行事・習慣等は記録されることが少なく、その起源とされるものは地元の有名な人物や歴史的事象に関連付けて語られる、いわゆる伝承に過ぎないのが大半です。
<参考文献>
佐賀県栄養保健推進協議会『佐賀の郷土料理』昭和59年
佐賀県教育委員会 佐賀県中学生郷土学習資料『佐賀を「知る」、「発見する」、「好きになる」佐賀巡り』平成30年
佐賀県教育委員会編『佐賀県の民俗』下巻 昭和49年
志津田藤四郎『佐賀の方言』上巻 佐賀新聞社 昭和45年
白石史談会編集・発行『白石地方の方言』平成3年
福山裕『佐賀弁一万語』佐賀新聞社 平成7年
PDF形式のファイルをご覧いただくには、アドビ システムズ社から無償提供されているAdobe ReaderTM(別ウインドウが開きます)プラグインが必要です。
このページに関するお問い合わせ先 生涯学習課 生涯学習係 電話(直通):0952-84-7129