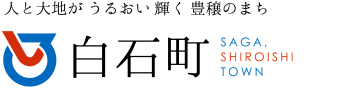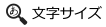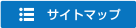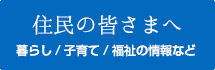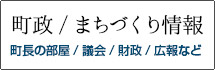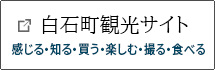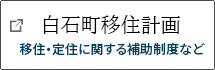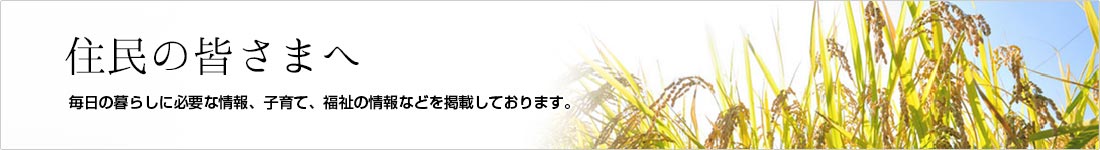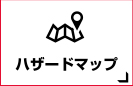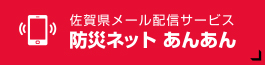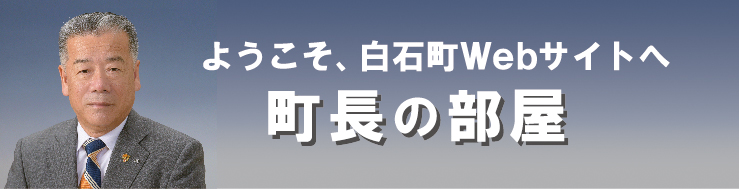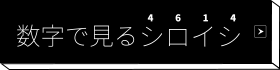あるある文化財VOL.184 長崎本線
日本における鉄道の始まりは、明治5年(1872)に開通の東京新橋(しんばし)―横浜(よこはま)間であり、鉄道の敷設は、国・民間によって全国で進められていきました。九州においても鉄道建設への熱が高まり、明治21年(1888)に民間の九州鉄道株式会社が免許を受け、同年博多(はかた)―久留米(くるめ)間の鉄道敷設工事が着工され、翌明治22年(1889)に開業し、九州における鉄道輸送が始まりました。上記の区間において田代(たしろ)駅、鳥栖(とす)駅(いずれも現:鳥栖市)が設置され、佐賀県で最初の鉄道建設となりました。
九州鉄道株式会社は、鳥栖―佐賀間を明治24年(1891)に、佐賀―武雄(たけお)間を明治28年(1895)に、武雄―早岐(はいき)間を明治30年(1897)に開通させ、明治31年(1898)に長崎線(ながさきせん)(鳥栖―長崎間)が全通しました。この時の長崎線は、鳥栖から武雄、早岐、大村(おおむら)を通り長崎に至るもので、現在の佐世保(させぼ)線、大村線にあたります。このルートでの建設が進んだ要因の一つとして、長崎県佐世保に鎮守府(ちんじゅふ)の設置が明治19年(1886)に決定したことが挙げられます。鎮守府とは旧日本海軍が軍港都市に設けた本拠地で、工場や病院など様々な施設の運営・監督を行いました。国内では佐世保の他に、横須賀(よこすか)・舞鶴(まいづる)・呉(くれ)に設置されました。
白石町を通る現在の長崎本線は、当初は有明平坦(へいたん)線と呼ばれていました。有明海沿岸に鉄道を通すことは、沿岸の住民にとっての悲願でした。しかし、当時佐賀県内を通る長崎線(現:佐世保線)のどの場所を起点にするかについては、大正14年(1925)に鉄道省が肥前山口(ひぜんやまぐち)駅から分岐させる計画を発表しますが、佐賀市郡はこれに反対し、佐賀駅から分岐させ久保田(くぼた)(現:佐賀市)、芦刈(あしかり)(現:小城市)、福富(現:白石町)を通るよう求め、起点変更運動が起こりました。鉄道省の計画を支持する杵島郡内の龍王(りゅうおう)・錦江(にしきえ)・北有明・南有明・福治(ふくじ)・六角(ろっかく)・須古(すこ)各村(いずれも現:白石町)と小田(おだ)・佐留志(さるし)各村(いずれも現:江北(こうほく)町)を中心にして「肥前山口駅起点維持同盟会」が結成され、中央政界に対し計画どおりの着工を求めました。結果的に佐賀駅に起点を設け分岐させる案は貴族院の反対により却下され、鉄道省の計画どおり肥前山口駅が有明平坦線の起点となりました。
有明平坦線の肥前山口―福治―肥前竜王間の工事は、昭和元年(1926)に始まりました。一級河川の六角川に昭和5年(1930)に架橋(かきょう)された六角川橋梁(きょうりょう)は現在においても現役です。六角川橋梁については「あるある文化財第7号」にて紹介しています。軟弱地盤(なんじゃくじばん)のため、盛土が崩れる、沈下するなど難工事の連続だったそうです。
難工事の末、昭和5年(1930)に肥前山口―福治―肥前竜王間が開通し、福治駅(現:肥前白石駅)、肥前竜王駅が設置され、有明平坦線の一部が開業しました。その後も白石町と鹿島(かしま)市を隔てる二級河川の塩田川への橋梁の架橋など工事は続けられ、昭和9年(1934)12月に有明平坦線は全線開通し、鳥栖―肥前山口―肥前鹿島―諫早(いさはや)―長崎間は、長崎本線と呼称されることになりました。全線開通により長距離の移動が容易になり、人的物的交流が一層の高まりを見せます。
長崎本線では、開業より蒸気機関車(SL)、ディーゼル機関車(DL)の牽引(けんいん)により運行されていましたが、昭和50(1975)7月1日に佐世保線と共に電化がされ、電気機関車(電車)による運行が開始されました。昭和61年(1986)には塩田川橋梁が三角形の鋼材を組み合わせたワーレントラス構造を持つ現在の橋梁となりました。平成28年(2016)には、肥前白石駅の旧駅舎(「あるある文化財第6号」にて紹介)が解体され現在の新駅舎になるなど、時代と共に変化しつつ公共交通機関の一端を担い続けています。
三角形のワーレントラス構造の長崎本線塩田川橋梁
〈参考文献〉
運輸省編『昭和51年度運輸白書』
佐賀県教育委員会編『佐賀県の近代化遺産-佐賀県近代化遺産(建造物等)総合調査報告書-』平成14年
佐賀県史編さん委員会『佐賀県史 下巻』昭和42年
白石町史編纂委員会『白石町史』昭和49年
PDF形式のファイルをご覧いただくには、アドビ システムズ社から無償提供されているAdobe ReaderTM(別ウインドウが開きます)プラグインが必要です。
このページに関するお問い合わせ先 生涯学習課 生涯学習係 電話(直通):0952-84-7129