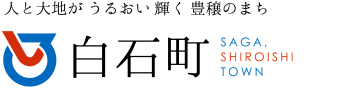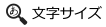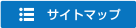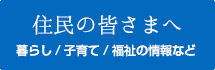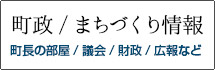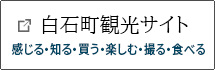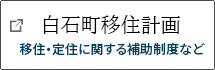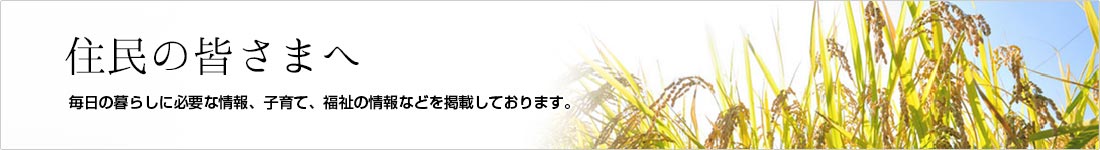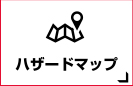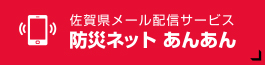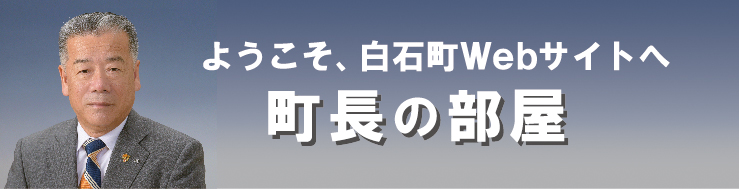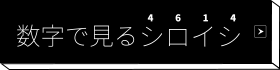あるある文化財VOL.178 陽線刻地蔵菩薩坐像板碑(2)
前回は、馬洗(もうらい)・法泉(ほうせん)寺の2基、嘉瀬川(かせがわ)・安福(あんぷく)寺の1基と、大町町福母( ふくも)の応安(おうあん)6年(北朝年号-1373)銘の1基、計4基の陽線刻地蔵菩薩坐像板碑(ようせんこくじぞうぼさつざぞういたび)を御紹介しました。
白石町と六角川を挟んだ対岸の大町町に、ほぼ同じ姿態で、なおかつ、応安6年前後の短い期間に制作されたと考えられる板碑が存在する理由のひとつとして、南北朝時代(14世紀後半)の杵島郡内の軍事的動向も考えられるでしょうか。
応安4年(1371)11月22日に北朝方の今川頼泰(いまがわよりやす)(九州探題(たんだい)今川了俊(りょうしゅん)の弟)が呼子に上陸、12月15日杵島郡白米(白毛)岳(白石町大字田野上(たのうえ)・島津(しまづ)城跡?)に陣し、次いで同21日に同郡椿(つばき)(武雄市武雄町大字永島)に陣を移し、同23日に同郡武雄之城(武雄市武雄町大字武雄)、同27日に同郡牟留井(むるい)城(所在地不明)で武雄の後藤光明(みつあき)と戦いました。翌5年(1372)正月13日に陣を杵島郡柏(かしわ)岳(武雄市武雄町大字富岡(とみおか))に移し、2月13日の同郡烏帽子(えぼし)岳(武雄市武雄町大字中野(なかの))の合戦で南朝方の菊池武正(きくちたけまさ)を破っています。このように、応安4・5年には、杵島郡内で北朝方と南朝方との間で激戦が行われたのです。
以上のように、大町町に「応安」という北朝年号が使用された地蔵菩薩坐像板碑があり、姿態はそれとほぼ同一で、なおかつ同時期と考えられる板碑が白石町内にも存在するという事実は、今川頼泰の杵島郡内における軍事行動と結びつけて考えられるでしょうか。
町内には、記述の3基の地蔵菩薩坐像板碑の他に、馬田(うまだ)・淡島(あわしま)神社で1基が確認されています。六角川堤防側の榎(えのき)の根元にありましたが、平成4年度の六角川河川改修工事に伴い、淡島神社と共に南側の現在地へ移築されました。
馬田・淡島神社の陽線刻地蔵菩薩坐像板碑
板碑は現在高46cm、幅57cm、厚さ約10cmと他の3基と比較すると小型であり、陽線刻された地蔵菩薩坐像も一回り小型となっています。円光は頭部のみ、蓮華座(れんげざ)に座り、右手に錫杖(しゃくじょう)、左手に宝珠(ほうじゅ)を持つ坐像は、円光・頭頂部・額・錫杖と返花(かえりばな)が付く蓮華座は陰刻です。
この板碑にも年号等は刻印されておらず、制作年代は不明ですが、他の3基よりも時代的に下る15世紀代でしょうか。
因みに、この板碑のある淡島神社の総本社は、少彦名命(すくなひこなのみこと)・大己貴命(おほなむじのみこと)・息長足姫命(おきながたらしひめのみこと)(神功皇后(じんぐうこうごう))を祭神とする、和歌山市加太(かだ)に鎮座する淡嶋神社です。大藤時彦氏の「淡島信仰」によると、「この神は住吉神社の妃神で、白帯下(こしけ)の病のためここに流されたという。そのため婦人の下の病、安産祈願、縁結びなどに利益あるとされている」淡島信仰が、江戸時代に御神体の人形を祀った厨子(ずし)を背負い、神徳を説いて廻った淡島願人(あわしまがんにん)と呼ぶ人々により全国に広がりました。
〈史料〉
瀬野精一郎編『南北朝遺文』-九州編‐第5巻 東京堂出版 昭和63年
〈参考文献〉
「淡嶋神社」ホームページ
大藤時彦「淡島信仰」『国史大辞典』第1巻(あ~い) 吉川弘文館 昭和61年
佐賀県教育委員会『佐賀県の中近世城館』第3集各説編2(小城・杵島・藤津地区)平成26年
PDF形式のファイルをご覧いただくには、アドビ システムズ社から無償提供されているAdobe ReaderTM(別ウインドウが開きます)プラグインが必要です。
このページに関するお問い合わせ先 生涯学習課 生涯学習係 電話(直通):0952-84-7129