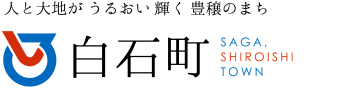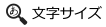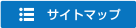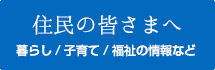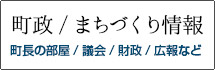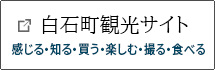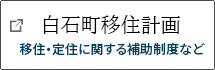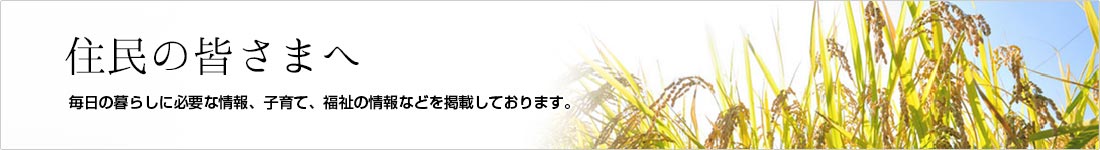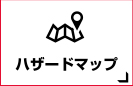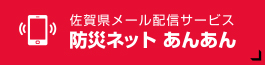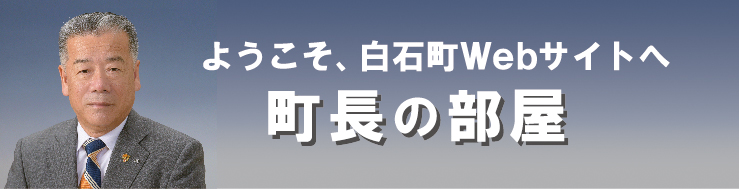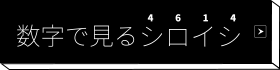あるある文化財VOL.198 トヨタマヒメ(豊玉姫)
佐賀藩の直営で干拓された六府方新搦地(ろふかたしんからみち)の鎮護のために、天明(てんめい)5年(1785)8月、鬼門(きもん)(北東)の地に建立された石祠(ほこら)が、現在の東六府方区・龍(りゅう)神社の前身になります。建立から8年後の寛政(かんせい)5年(1793)に再建され、現在は本殿裏に移設されている石祠(町重要文化財)には、御祭神は「豊玉姫之尊」(トヨタマヒメノミコト)と記され、龍神社々務所発行パンフレットには「豊玉姫命」(トヨタマヒメノミコト)と表記されています。
東六府方区・龍神社「豊玉姫之尊」石祠(白石町重要文化財)
また、龍王崎(りゅうおうざき)先端に鎮座する竜王・海童(かいどう)神社(江戸時代後期‐19世紀の「白石南郷室島(むるしま)村」絵図には「龍王」と表記)も、父海神(わたつみ)豊玉彦命(トヨタマヒコノミコト)と共に娘豊玉姫命が御祭神として祀られています。「尊」と「命」は、いずれも高貴な方に尊敬の意を表わして添える語です。
竜王・海童神社
このトヨタマヒメが登場する話として、御存知の方も多いと思われますが、「海幸(うみさち)山幸(やまさち)」があります。この話の原点は、和銅(わどう)5年(712)成立の『古事記(こじき)』上巻と養老(ようろう)4年(720)成立の『日本書紀(にほんしょき)』神代(かみよ)下 第10段に見られます。あらすじは両者ほぼ同じですが、呼び名とその漢字表記が異なります。ここでは、『日本書紀』に基づく呼び名を使用してその内容を記してみます。
弟ヒコホホデノミコト(彦火火出見尊‐山幸)は、交換した兄ホノスソリノミコト(火闌降命‐海幸)の釣針を失くし怒りを買ったが、シホツツノヲヂ(塩土老翁)の教えにより海神の宮に行くことができた。海神トヨタマビコのもてなしを受け、失くした釣針も取り戻せた。海神の娘トヨタマビメと結婚し3年間住んだが、故郷のことを思って嘆いた。海神はヒコホホデノミコトに呪力の有る玉を与え、故郷に帰した。トヨタマビメは、妊娠を告げ、必ず訪れるから海辺に産屋(うぶや)を作って待つように頼んだ。
故郷に帰ったヒコホホデノミコトは、海神からもらった玉により兄を従えた。トヨタマビメは約束どおり、妹タマヨリビメ(玉依姫)と一緒に海辺に行った。出産前にトヨタマビメは、出産する姿を決して見ないでとヒコホホデノミコトにお願いした。しかしヒコホホデノミコトは我慢できず、密かに盗み見ると、トヨタマビメは龍(たつ)(第10段別書には八尋(やひろ)の大熊鰐(わに)、または八尋大鰐(やひろのわに))となっていた。
トヨタマビメは恥じて、産まれた子を草(かや)に包んで海辺に捨てて、海神の宮に帰ってしまった。その子を、ヒコナギサタケウガヤフキアヘズノミコト(彦波瀲武鸕鷀草葺不合尊)と名付けた、という内容です。この名は、産屋を鸕鷀(う)(鵜(う))の羽を草として葺(ふ)いていたが、屋根の頂上部分を未だ葺き合わせないうちに生まれ、草に包まれ波瀲(なぎさ)に捨てられた子、という意味です。
神代下 第11段には、後にヒコナギサタケウガヤフキアヘズノミコトは母トヨタマビメの妹タマヨリビメを妃とし、四人の男子、ヒコイツセノミコト(彦五瀬命)、イナヒノミコト(稲飯命)、ミケイリノノミコト(三毛入野命)、カムヤマトイハレビコノミコト(神日本磐余彦尊)が産まれた、とあります。四男のカムヤマトイハレビコノミコトは、後の神武(じんむ)天皇にあたります。
県内でトヨタマヒメを主祭神とする神社としては、嬉野市嬉野町に豊玉姫神社が鎮座しています。その縁起や何故内陸部にあたる嬉野に創建されたのか不明ですが、その立地の故からか美肌の女神としても信仰されています。町内に鎮座する龍神社及び海童神社は、トヨタマヒメが海神の娘であることから、海・水の女神として、言い換えれば龍神社は上述のとおり干拓地の鎮護神として創建され、海童神社は海上交通の安全や豊漁の神として創建されたと考えられます。
<参考文献他>
青木和夫他校注 日本思想体系1『古事記』岩波書店 昭和57年
坂本太郎他校注 日本古典文学大系67『日本書紀』上 岩波書店 昭和56年
佐賀県立図書館所蔵「白石南郷室島村」絵図
PDF形式のファイルをご覧いただくには、アドビ システムズ社から無償提供されているAdobe ReaderTM(別ウインドウが開きます)プラグインが必要です。
このページに関するお問い合わせ先 生涯学習課 生涯学習係 電話(直通):0952-84-7129