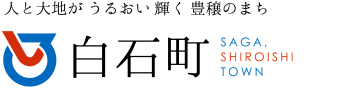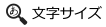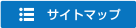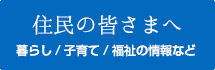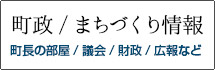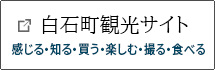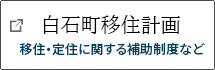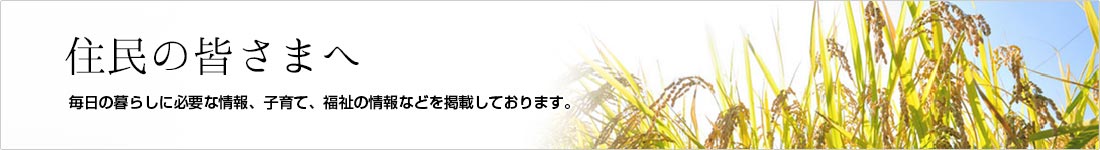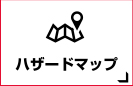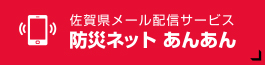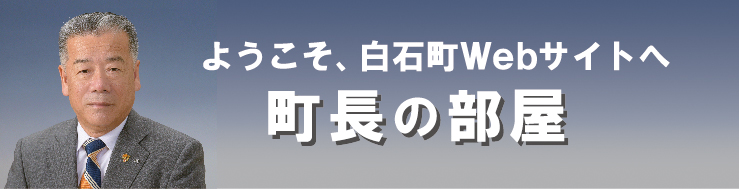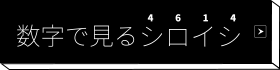あるある文化財VOL.187 白石町内の浮立
令和2年11月23日、佐賀市文化会館で第3回佐賀県伝承芸能祭が行われました。この芸能祭は、各地域の伝承芸能が一堂に会し、ステージで実演を行うもので、県民が伝承芸能に触れる機会を作ろうと開催されています。今年の芸能祭は、出演団体の一つとして有明地域の戸ヶ里(とがり)浮立(ふりゅう)保存会が出演しました。当日は、20分間の実演を行い、会場は浮立の音色に包まれました。その熱演が評価され、「サガテレビ社長賞」を受けられました。
ところで、今回の芸能祭では県内9団体が出演し、そのうち4団体が名称に「浮立」と明記されています。出演団体のうち、約半分が浮立だったわけです。また、平成30年度に佐賀県が行った佐賀県の伝承芸能実態調査によると、芸能の種類の質問に対して複数回答ではありますが、県内伝承芸能団体のうち7割が「浮立」と回答しています。この状況からもわかる通り、「浮立」は佐賀県を代表する民俗芸能といえます。
この「浮立」とは、「みやびやかな」の意味である「風流(ふうりゅう)」からきています。平安時代から中世には「ふうりゅう」ではなく「ふりゅう」と読まれるようになり、祭りの山車(だし)などに施された華美な装飾やその祭りの警固者の奇抜な衣装などを総称するようになります。いつしかそれが、造形美を誇示(こじ)した祭りや芸能を風流(ふりゅう)と呼ぶようになりました。「浮立」は「風流」の当て字で、『世界大百科事典』では「鬼面の者や仮装の者が笛・太鼓・大小鼓(つづみ)・鉦(かね)などで囃(はや)されて踊る芸態は、一種の囃子物といえよう」と紹介されています。
佐賀県民にとって身近な浮立ですが、実は多種多様で様々な種類があります。この多彩な佐賀県内の浮立を様々な方が分類しているのですが、今回は分類基準が明確な佛坂氏の分類を参考にしたいと思います。佛坂氏は、浮立を笛・鉦・太鼓などの楽器を用いて囃す囃子そのものをさす場合((1)一声(いっせい)浮立、(2)鉦浮立)と、同様な囃子に合せて所作を伴う踊りや舞が付くもの((3)踊浮立、(4)玄蕃一流浮立、(5)面浮立、(6)獅子浮立、(7)行列浮立、(8)広瀬浮立など)、その他浮立系の芸能((9)荒踊(あらおどり)・かんこ踊、(10)狂言など)の大きく3つに分類しています。紙面の都合上、すべてを紹介するのは困難なので、白石町内で主に伝承されている「(1)一声浮立」、「(2)鉦浮立」についてご紹介したいと思います。
一声浮立とは、皮浮立、太鼓浮立とも呼ばれる大小の太鼓や鼓が中心の浮立です。この「一声」とは能の用語で、演者の登場に際して、大小の鼓と笛が演奏するお囃子のことです。演奏する楽器やお囃子が似ていることから、大小の鼓の合奏が中心で笛が加わる浮立を一声浮立と呼んでいます。この浮立は、県西部有明海沿岸一帯に伝承されています。
鉦浮立とは、笛、太鼓に合せて、鉦が囃される浮立で、鉦が中心の浮立です。県東部の鉦浮立(鳥栖市(とすし)宿町(しゅくまち)の鉦浮立など)では、大きさの同じ鉦を同時に打ちます。しかし、白石町も含む佐賀市以西の鉦浮立では大きさの異なる鉦を用いますし、打数もそれぞれ異なります。
令和2年10月19日、戸ヶ里浮立保存会が浮立を奉納した稲佐(いなさ)神社では、新型コロナウイルス感染症対策をしたうえでお供日(くんち)が行われました。令和2年の稲佐神社の流鏑馬(やぶさめ)では、疫病(えきびょう)退散の「感染症早期終熄(しゅうそく)祈願的」が用意され、射手(いて)の放った矢は見事命中しました。令和2年のお供日は例年通りとはいきませんでしたが、変わらない参拝者の笑顔がありました。
令和2年稲佐神社秋季例祭で浮立を奉納する戸ヶ里浮立保存会
〈参考文献〉
天野文雄、山路興造「ふりゅう風流」下中直人編『世界大百科事典』平凡社 平成19年
佐賀県文化・スポーツ交流局 文化課『佐賀県伝承芸能実態調査報告書』平成31年
佛坂勝男「佐賀県の浮立」『民俗芸能』通刊66号 昭和60年 ほか
PDF形式のファイルをご覧いただくには、アドビ システムズ社から無償提供されているAdobe ReaderTM(別ウインドウが開きます)プラグインが必要です。
このページに関するお問い合わせ先 生涯学習課 生涯学習係 電話(直通):0952-84-7129