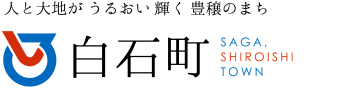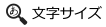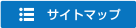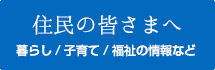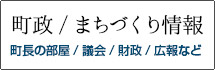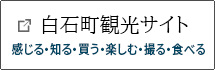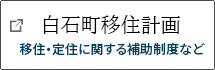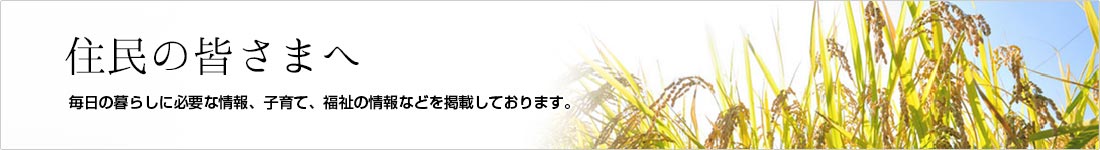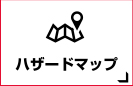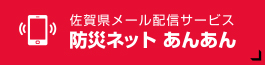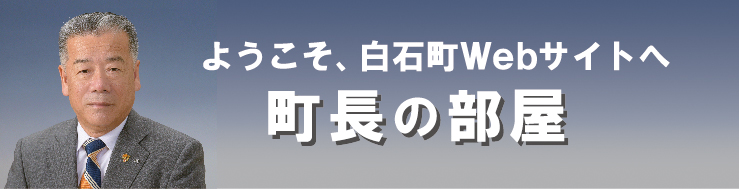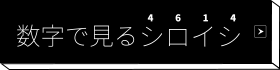あるある文化財VOL.182 六千間土居跡
町東部には現在は役目を終え、道路や畑として使用されている干拓堤防跡が複数あり、江戸時代に築堤された中で大規模
な堤防跡が六千間土居跡(ろくせんげんどいあと)(18世紀後半築堤)です。
六千間土居跡は、名前のとおり堤防の長さが六千間以上(約12km)におよぶ干拓堤防跡です。六角川河口から廻里江(めぐりえ)川河口までを結ぶ大規模なものでした。その堤防跡の一部は、現在国道444号線(新観音~新興(しんこう)付近)となっており、住民の生活を支える道路として使用されています。

六千間土居跡(赤線部分) 矢印地点は平成29年調査箇所
六千間土居の築堤は、佐賀藩の直営事業として行われました。天下泰平の江戸時代においては、武力により領地を拡大することは不可能なことでした。多くの藩においては、干拓や開墾による新田開発、蝋燭(ろうそく)の原料となる櫨(はぜ)などの商品作物の生産を奨励(しょうれい)し藩の財政健全化に務めました。佐賀藩においても8代藩主鍋島治茂(なべしまはるしげ)により、殖産興業機関である六府方(ろくふかた)が天明(てんめい)3(1783)年に設置されました。六府方は山方及び里方、牧方、陶器方、搦方(からみがた)、貸付方、講方の6つの部署があり、干拓を担当したのが搦方でした。福富地域の地名である六府方は、搦方による堤防築堤により生まれた干拓地であるためこの名となりました。
干拓堤防の性質上、新たな干拓堤防が海側(東側)に築かれると、役目を終えた堤防は、道路や新堤防の資材として使用されるなど、徐々に姿を消していきました。六千間土居跡も例外ではなく、昭和期に行われた圃場(ほじょう)整備事業によって更に姿が失われたと思われます。
平成29年、道の駅しろいし進入路建設に伴う発掘調査により、六千間土居の護岸表面を覆っていた石組みが出土しました。その場所は畑として使用されており、長期間に渡り地中に埋没した状態でした。石組みに使用された石材は、赤みがかったもので通称赤石(あかいし)と呼ばれる安山岩質凝灰角礫岩(あんざんがんしつぎょうかいかくれきがん)でした。この赤石は直線距離で約9km離れた多久市納所(のうそ)で産出され、牛津川を利用し現地まで輸送されたと思われます。輸送された赤石は現地において短冊(たんざく)形状に最終的に加工され、護岸に設置されたと思われます。
またこの赤石は、同じく8代藩主治茂の時代に改修された佐賀城外堀の石垣や、孫の10代藩主直正(なおまさ)の時代に造営された佐賀城本丸御殿(ほんまるごてん)の基礎石として使用されるなど、佐賀城での使用が確認されています。
赤石護岸(東から)
堤防護岸の石組みの直下からは松の杭や胴木、竹杭が確認されており築堤の際に堤防の沈下を防ぎ、強化するため使用されたと思われます。
内部の松杭や胴木、竹杭(北から)
多大な労力と資材を投入した干拓によって生まれた新田は佐賀藩に大きな富をもたらし、幕末の佐賀藩の近代化をすすめる源泉となりました。
皆さんが普段何気なく歩かれている道も先人の築いた堤防跡かもしれません。
※写真は、平成29年調査当時のものであり、現在見ることはできません。
<参考文献>
九州農政局有明干拓建設事業所 『有明干拓史』昭和44年
PDF形式のファイルをご覧いただくには、アドビ システムズ社から無償提供されているAdobe ReaderTM(別ウインドウが開きます)プラグインが必要です。
このページに関するお問い合わせ先 生涯学習課 生涯学習係 電話(直通):0952-84-7129