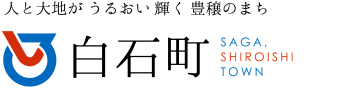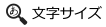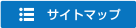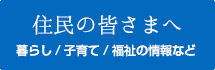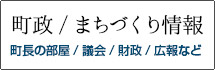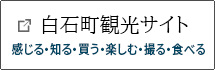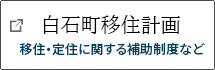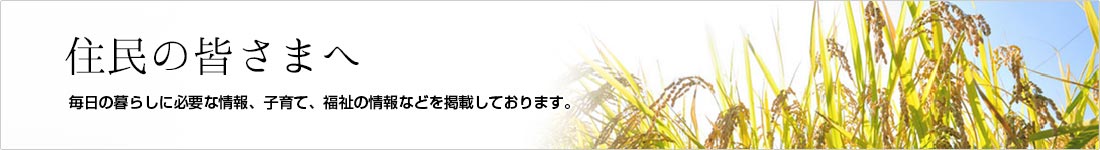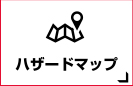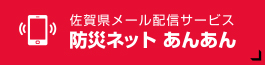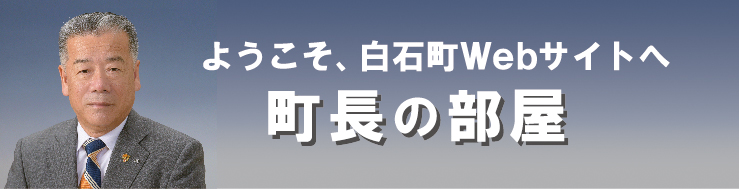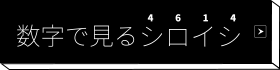龍造寺信周(りゅうぞうじのぶかね)
天文元年(1532)~慶長13年(1608)
隆信(たかのぶ)の異母弟で、須古(すこ)鍋島家初代。天正12年(1584)の兄隆信が島原の沖田畷(おきたなわて)で戦死した後、柳河(やながわ)城に引き籠った鍋島信生 (なべしまのぶなり=直茂・佐賀藩祖)に佐賀に戻るよう説得したのは信周である。信周外の龍造寺一門や隆信嫡男政家(まさいえ)が信生に起請文(きしょうもん)を提出することにより、信生が国政の実見を握っていくこととなった。
天正15年(1587)の豊臣秀吉(とよとみひでよし)による九州平定を経た後であろう、同年に夫婦で逆修有耳五輪塔(ぎゃくしゅゆうじごりんとう)一対を法泉寺(ほうせんじ)に造立している。また、同17年(1589)頃には、それまでの受領(ずりょう)名「安房守(あわのかみ)」と名前「信周」をそれぞれ「阿波守(あわのかみ)」と「周光(ちかみつ)」に改名している。
文禄の役(ぶんんろくのえき=1592~1593)では、信周は佐賀城の留守を預かり、次男家誠(家俊・現地で病死)と三男松浦信明(松浦盛の養子・後の2代須古信明)が鍋島直茂に従い出兵した。この頃のことだと推定されるが、隆信が大規模な改修を加えた須古城に、信周は更なる改修を行っている。頂上の平坦部に多量に分布する文禄・慶長の頃(16世紀末から17世紀初頭)の瓦や、また中段東側の櫓台(やぐらだい)跡と推定される個所に残る本格的な石垣等からそのことが窺える。
信周が再建したとされる陽興寺(須古鍋島家菩提寺)には江戸時代中期(18世紀)以降の、また法泉寺には90回忌に当たる元禄10年(1697)作の木造坐像(ざぞう)がそれぞれ安置されている。
陽興寺所蔵信周坐像=広報白石H23.5月号(通常は非公開)

法泉寺所蔵信周坐像(通常は非公開)
※ 写真画像について、無断転載を固く禁じます。
このページに関するお問い合わせ先 生涯学習課 生涯学習係 電話(直通):0952-84-7129