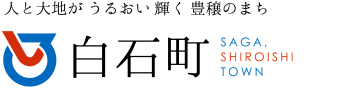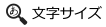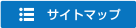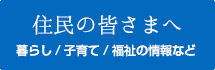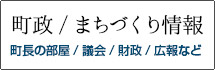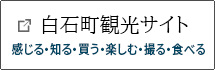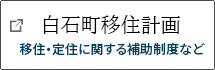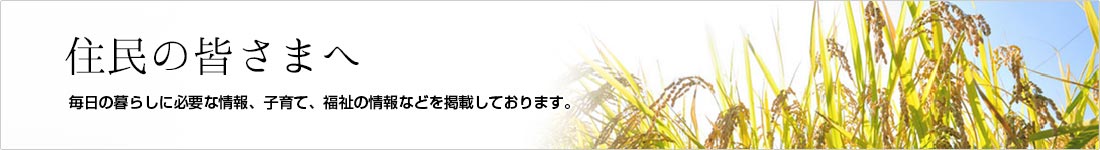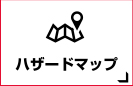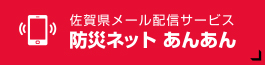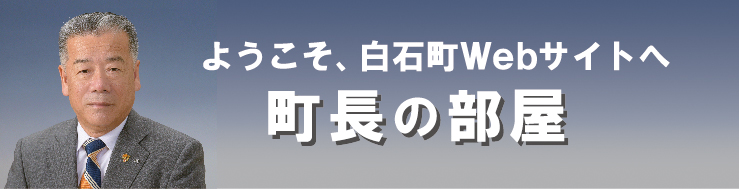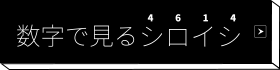介護保険
介護保険制度とは
介護保険制度は、急速な高齢化に伴い深刻化する高齢者の介護を社会全体で支えるため平成12年度に創設された社会保障制度です。
この制度の特徴として、
- 介護が必要になっても自立した生活が営めるよう支援する。
- 家族の介護の負担を軽減し、介護を社会全体で支える。
- 必要なサービスを自由に選んで、医療や福祉の介護サービスを総合的に利用できる。
などがあります。
介護保険制度は介護を要する高齢者とその家族を支えるしくみとして定着してきましたが、要介護認定者は増え続け、高齢化はさらに進むと予想されます。急激に進む高齢社会の中で、介護保険は病気や要介護状態にならないための予防に取り組み、介護が必要な状態になっても状態の悪化を極力防ぐことで、高齢者ができる限りすこやかで自立した生活を送ることができるように支援します。
保険者
※介護保険に関する各種申請書のダウンロードや、詳しい内容がご覧になれます。
被保険者
40歳以上の人全てが加入対象になります。
第1号被保険者・・・65歳以上の人
第2号被保険者・・・40歳以上64歳以下の人
介護保険料と納付方法
第1号被保険者の保険料は、所得に応じて決定されます。原則として年金から納めますが、年金額によって納め方は2種類にわかれます。また、第1号被保険者として納める保険料は65歳になった月(65歳の誕生日の前日が属する月)の分からです。
| 特別徴収 年金が年額18万円以上の人 |
年金の定期払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。老齢基礎年金・厚生年金などの老齢(退職)年金のほか、遺族年金、障害年金も特別徴収の対象となります。 |
|---|---|
| 普通徴収 年金が年額18万円未満の人 |
送付される納付書で介護保険料を市町村に個別に納めます。 お支払いは、口座振替が便利です。保険料の納付書、預貯金通帳、印鑑を持って口座をお持ちの金融機関や町の窓口で手続きをしてください。 |
第2号被保険者の保険料は、国民健康保険料などの各種医療保険の算定に基づいて設定されます。納め方は、医療保険と一括して支払うことになります。
申請から利用までの流れ
介護(予防)サービスの利用は、市町への要介護認定の申請からはじまります。
認定調査や審査を経て、要介護・要支援・非該当といった認定結果にそったサービスを受けることになります。
1要介護(要支援)認定の申請をします。
サービスの利用を希望する人は、介護保険担当の窓口で「要介護(要支援)認定」の申請をします。
2申請を受けて、調査や審査会で判定が行われます。
認定結果は次の手順で決定されます。
(1) 認定調査
心身の状態を調べるために担当の調査員が訪問して本人や家族などへの聞き取り調査が行われます。
(2) 主治医意見書
主治医から心身の状況について意見書を作成してもらいます。
(3) 審査・判定
認定調査の結果や主治医意見書をもとに「介護認定審査会」で介護の必要性や程度について審査が行われます。
3認定結果をお知らせします(原則として、申請から30日以内に、介護保険事務所から結果が郵送されます。)
| 要支援1・2 | 生活機能の低下が軽く、介護予防サービスで改善する可能性が高い人など。 |
|---|---|
| 要介護1~5 | 介護サービスによって、生活機能の維持・改善をはかることが適当な人など。 |
| 非該当 | 生活機能の低下により将来的に要支援などへの移行する危険性のある人など。 |
4ケアプラン作成
要支援1・2及び要介護1~5の人について、どんなサービスをどのくらい利用するのかというケアプラン
を作ります。
| 要支援1・2の人 | ケアプラン作成を白石町地域包括支援センターが担当します。 |
|---|---|
| 要介護1~5の人 | ケアプラン作成を居宅介護支援事業所(ケアマネージャー)が担当します。 |
5サービスの利用
ケアプランに基づき、介護サービスまたは介護予防サービスを利用します。
原則としてサービス費用の1割が自己負担となります。
食事代の一部などは自己負担となります。
※非該当という結果の出た人は、長寿社会課の行う事業に参加することができます。
サービスの種類
在宅サービスと施設サービスに分けられます。
要介護状態の人・・・在宅サービスと施設サービスの両方が受けられます。
要支援状態の人・・・在宅サービスのみ受けられます。
このページに関するお問い合わせ先 長寿社会課 高齢者係 電話(直通):0952-84-7117