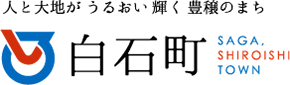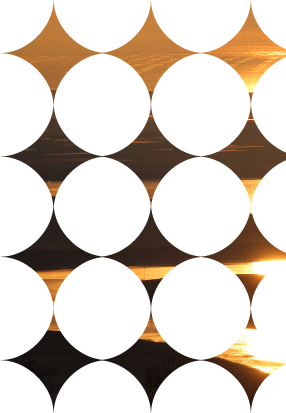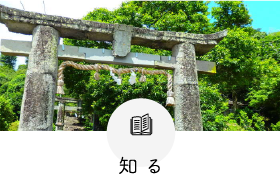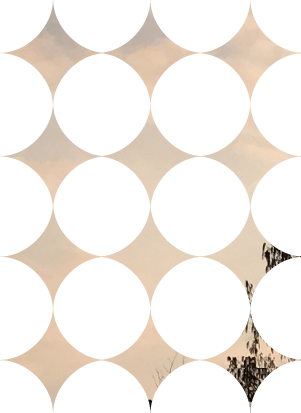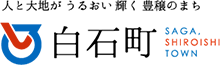須古寿し

今も祭りやお祝い事では欠かせない大切な郷土料理
伝承によれば500年以上前、須古地区の領主が領内の農民をとても大切にし、米の品質改良に尽力したそうです。そんな領主の愛情に感謝し、領民たちは海の幸、山の幸を使ってすしを作り、領主に献上したと言われています。この「須古寿し」は連綿と500年もの間、母から子へ、子から孫へと受け継がれ、今も祭りやお祝い事では欠かせない大切な郷土料理です。「もろふた」と呼ばれる木箱につくり、専用の木べらですくって取り分けるのが特徴的で、地元のさまざまな具材がのった箱ずしのスタイルです。有明海のムツゴロウをはじめ、しいたけ・ごぼう・奈良漬 ・紅しょうが等、さまざまな具材がのった贅沢な味わいが楽しめます。本来はムツゴロウのかば焼きを具材に使いますが、近年はムツゴロウが手に入りにくいため、エビやコノシロ等で代用されることもあります。
令和6年度に「100年フード(文化庁)」に「須古寿し」が認定されました。

※100年フードとは https://foodculture2021.go.jp/hyakunenfood/
文化庁で我が国の多様な食文化の継承・振興への機運を醸成するため、地域で世代を越えて受け継がれてきた食文化を、100年続く食文化「100年フード」と名付け、継承していくことを目指す取組。